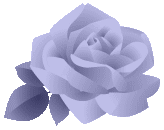窓辺の造花
<作:ペペロンターノ/朗読:いずっち>

<Photo:いずっち/Retouch:ペペロンターノ>
窓辺に咲く薔薇たちの生きざまを通して、「生きているということ」
について、自分なりに問うてみました。
童話風ですが、掲げたテーマは幅広い年齢層を意識しています。
終盤、ちょっぴりミステリー的(?)な要素も加えてみました。
音声ファイルを公開しておりますので、再生ボタンをクリックして
テキストと合わせてお楽しみください。
いずっちさんの表現力豊かな朗読と、ツボを押さえたBGMで、
作品世界のイメージが一層鮮やかに浮かび上がってくるかと思います。
中盤に挿入しております楽曲は、屋根裏の音楽家TACIAOによる
作曲演奏のピアノソロ曲『Il Dolce Nome』です。
※音声ファイルの登載許可を頂いております。
| 眩い朝の光が、レース越しに差し込む白い窓辺。透明な硝子の花瓶に、ピンクの薔薇の切り花が数本生けられていました。そのピンクの薔薇の中に、一本だけ青い薔薇が混じっていました。ピンクの薔薇たちは皆、部屋の中に顔を向けて咲いていましたが、何故か青い薔薇だけは窓の外を向いていたのでした。 薔薇たちは、煌めくような五月のそよ風を背に受け、友情の証を互いの葉っぱに綴り、覚えたての「愛」という単語を、可愛らしい蕊の弦で奏でていました。青い薔薇を除いては・・・ 死とは最も縁遠いオアシスで、栄華を誇っている絢爛華麗な花たちにも、命の終わりは平等に訪れるもの。小雨降るある夕方のこと、ピンクの薔薇たちは誰から聞くこともなく、自分たちの命が、もう残り幾ばくもないことを悟り始めていました。女王さながらに、気品と自信に満ち溢れていた笑顔は消え去り、誘惑と神秘を醸し出していた自慢の香水も、溜息と共にすっかり蒸発してしまっていたのです。青い薔薇を除いては・・・。 その夜、今まで一度も口を開かなかった青い薔薇が尋ねました。 「皆さん、どうしたのですか? 少し前までは、あんなに嬉しそうな表情で日々を謳歌していたのに、この頃元気がないですね。花弁もヨレヨレになってしまって、あの頃の美貌はもう見る影もないではないですか。失礼ですが、一気に老け込んでしまったように見えますよ。もしかして、ご病気ではないですか?」 すると、すぐ隣のピンクの薔薇が口を開きました。 「病気じゃないわ。命が尽きる時が来たの。そう、寿命が来たのよ」 少し驚いたような顔をして、青い薔薇が言いました。 「寿命? 寿命が近づいて来ると、そんな萎れた姿になってしまうのですか?」 「そうよ、私たちお花だけじゃないわ。この家に住んでいる人間や、時々庭先に現れる小鳥や猫、お花の蜜を運んでくれるミツバチやチョウにだって、全てに寿命はある。その命の終わりが近づいて来るに連れて、若かった頃の瑞々しさは影を潜め、光り輝いていた素肌も薄黒く色褪せて行ってしまうの。それが老いというものよ」 と、ピンクの薔薇は少し疲れたような表情を浮かべながら、声を振り絞るように答えました。 「おかしいなぁ。僕はあなた達よりも前からこの窓辺で咲いているけれど、全然色褪せないし元気なままでいますよ」 青い薔薇は不思議そうに、そして微かに勝ち誇ったような笑みを浮かべながら言いました。すると次の瞬間、ピンクの薔薇の花から意外な答えが返ってきたのでした。 「それは、あなたが本物の花ではないからよ」 「え?」と、驚いた表情の青い薔薇。 「生きている花ではないの。つまり造花ってこと。だから枯れないし死なないのよ。いいえ、死ねないの。それはとても悲しいことよ」 面食らった青い薔薇は、負けずに言い返します。 「僕が造花ですって? ・・・だとしても、死なないんだったら、それはむしろ喜ぶべきことじゃないですか! 僕は、明日も明後日も一年後も、いいえ、ずっとずっと先も、この美しい姿を保ち続けていられるのです。僕は永遠の命を神様から与えられたのです。それに比べて、あなたたち本物の花ときたら・・・」 青い薔薇の言葉が終わらないうちに、ピンクの薔薇が残りわずかな力を込めて、こう言いました。 「そうじゃないわ。限りある命だから愛おしいのよ。限られた時間の中で、目覚めの歌を歌い、生き物たちに希望や安らぎ与え、仲間同士で愛を育み、そして誇り高く散って行くの」 「そうよ、そうよ」と、黙っていた他のピンクの薔薇たちも賛同します。 「違うよ。僕は永遠の命の方が良いんだ!」 みんなの力に押されてか、孤立無援の青い薔薇は、今にも泣きそうになりながら必死で言い返します。 「でもね、それは本当の命じゃない。本当に生きるっていうのはね・・・」 そう言ったきり、ピンクの薔薇が二度と口を開くことはありませんでした。翌朝、青い薔薇が目覚めると、ピンクの薔薇たちはすっかりセピア色に色褪せ、すでに力尽きていました。窓の隙間から忍び込んで来た湿り気を帯びた風に、萎れきった花弁が音もなくそよいでいるだけでした。 それから、しばらく雨の時期が続いた後、その白い窓辺には夏が訪れ、秋が過ぎ去り、さらには冬が長い沈黙を留め、やがて、生まれたての春が羽音を立てながら舞い降りて来ました。その間、硝子の花瓶には、季節に合った美しい花が代わる代わる生けられ、あのピンクの薔薇たちと同じように、目覚めの歌を歌い、生き物たちに希望や安らぎ与え、仲間同士愛を育み、誇り高く散って行ったのです。 その一部始終を、青い薔薇は同じ花瓶の中でたった一人声を上げることなく、静かに見守っていました。始めの頃は、短い命を惜しげもなく散らして行く本物の花たちを哀れに思い、永遠の美貌と命を授かった自分自身を誇りに思っていた青い薔薇でしたが、季節の移り変わりと共に、その考えは次第に変わって行ったのです。 「僕は一体いつからここにいるのだろう? 何のために生まれてきたのだろう? 誰のために生きているのだろう? 本当に僕は生きているのだろうか?」 今朝もまた、青い薔薇は、周囲の花たちが短くも美しい命を終える瞬間に立ち会ったばかり。一年前のピンクの薔薇との会話を思い出しながら、この白い窓辺で、自分だけが何も変わることなく永遠に存在し続けることに、たとえようのない恐れを抱いていました。 そんな不安な日々に耐え忍んでいたある朝のことです。その部屋は、深い深い悲しみに包まれていました。白い窓辺にすぐ手が届きそうなところにはベッドがあり、その傍らには、やつれた表情の美しい女の人が座っていて、そのささくれだらけの十本の指には、白くか細い手がしっかりと握られていました。つい今しがたベッドの上で、白い手の主である少女の命の灯が、静かに燃え尽きたところだったのです。 少女の年頃は、十六、七といったところでしょうか。冷たくなっていく手を握っているのは、少女の母親でした。母親は、花が大好きな娘のために、年中季節の花を生け続けてきたのです。皮肉にも、今花瓶に生けられているのは、一年前と同じピンクの薔薇。しかも、丁度今が美の最盛期。まるで少女の命の灯を奪ったかのように、色鮮やかに咲き誇っています。 母親は何とも居た堪れない気持ちになって、ピンクの薔薇を花瓶から引き抜くと、窓の外に投げ捨ててしまいました。 その時です。一本だけ花瓶に残っていた青い薔薇の胸に、激しい痛みが走りました。まるで、自分の棘で心臓を突き刺したかのような痛みが、体中を駆け巡りました。ところが、間もなく痛みは治まり、やがて今まで感じたことのないような安らぎに包まれて行くのでした。 ふと自分の体に目をやると、艶やかだった緑の葉は醜く萎れ、神々しさを纏っていたはずの鮮やかな青い花弁は、残酷なほどにみるみる色を失い朽ちて行くではありませんか。にもかかわらず、青い薔薇は不思議と悲しいとは思いませんでした。 「これが・・・、生きているっていうことなのか・・・」 “朽ちる”ということは、造花だったはずの青い薔薇が、いつしか本物の生きている花に変わったというのでしょうか? いいえ、そうではありません。造花でも本物の薔薇でもなく、それは長い間、不治の病と闘いながら、明日をも知れない命の灯を必死で燃やそうと努力してきた少女の一念が作り出した幻だったのです。 他の花が部屋の中に顔を向けているのとは逆に、青い薔薇はいつも窓の外を向き、世の中の営みや季節の移ろいを少女の心に伝えていたのでした。誰にも知られることなく、たった一人で・・・。ですから、少女の命が尽きると共に、青い薔薇も同じ運命を辿ったのは、至極当然のことと言えるかもしれません。 でも・・・・、果たして、それだけのことだったのでしょうか? 命尽きた青い薔薇は、今部屋の中を向いています。それは初めてのことでした。すると不思議なことに、蕊の中から小さなミツバチが花粉だらけの顔をひょっこり出し、程なく、白い窓辺から元気に飛び立って行ったのです。 青く澄んだ五月の空の彼方へ消えて行くミツバチの姿を、愛おしむように見守っている母親の姿がそこにありました。少女の手を優しく握りしめたまま、未来(あす)へと紡がれて行くべき、命の奇跡を信じて・・・。 さて、皆さんは青い薔薇の花言葉、ご存知ですか? それは、奇跡・・・ |
Fin